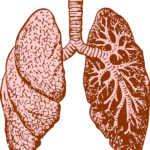救急外来でよく見かける疾患として、「過呼吸症候群」が挙げられます。
僕が持っているイメージは、「過呼吸になって、CO2が飛んでいって、呼吸性アルカローシスになって、Caが下がることで筋肉の興奮性が上がって、テタニー(手足のしびれ)がおきる」という程度でした。「呼吸性アルカローシスになって、Caが下がる」ってのがテキトーですよね笑
また、カルシウムに関するややこしい概念の1つに、「補正Ca」があって、
補正Ca = 実測Ca + 4 – Alb(アルブミン) …(1)
という式が成り立つのが有名です。
正直なところなぜ”補正”なんてことをしないといけないかよく分かっていなかったのですが、この度勉強していると「過換気症候群」の機序と併せて理解が深まってきました。
そもそも、筋肉の興奮性を上下させる等の「生理的活性」を持つのは、イオン化Ca(Ca2+)です。そして、イオン化Ca(Ca2+)はアルブミンと結合している状態(「Alb結合Ca」とここでは呼ぶ)だと「生理的活性」を持ちません。
そして、実測Caは
実測Ca = イオン化Ca(Ca2+) + Alb結合Ca …(2)
の総和です。繰り返しますがそのうち「生理的活性」を持つのは、イオン化Ca(Ca2+)のみ。
過換気症候群になり、呼吸性アルカローシスになると、もともと負に帯電しているAlbは電気的平衡の影響でさらに負の電荷を帯びます。
ごくごく大雑把なイメージは、
Alb– + H+ ⇔ Alb
両辺にOH–を足して、
Alb– + H2O ⇔ Alb + OH–
となります。呼吸性アルカローシスになると、OH–が増えるので、平衡は左に傾きます。
その結果、負の電荷を持つAlb–の量が増え、これが正の電荷を持つイオン化Ca(Ca2+)と結合することで、Alb結合Caとなり、イオン化Ca(Ca2+)が減少し、その結果、テタニーが起きる、という理屈です。
また、補正CaはAlbの値が小さい(4mg/dL以下)の時に、Albと結合するイオン化Ca(Ca2+)が減少するため、相対的にイオン化Ca(Ca2+)が増加、つまり活性を持つCaが増加するため、実測Caを用いることでCaの影響を過小評価してしまわないように用いる値です。
だいぶ胡散臭い理解ですが、頭の中がちょっとスッキリした気がします。(2)の式を(1)の式に代入すると、、、??となるので深くは考えないようにしましょう笑
関連する2つの事柄がちょっとしたことでつながると記憶が強化されて気持ちいいなぁ、と思います。
ランキングに参加しています。よろしければクリックいただけると幸いです!

にほんブログ村

研修医ランキング